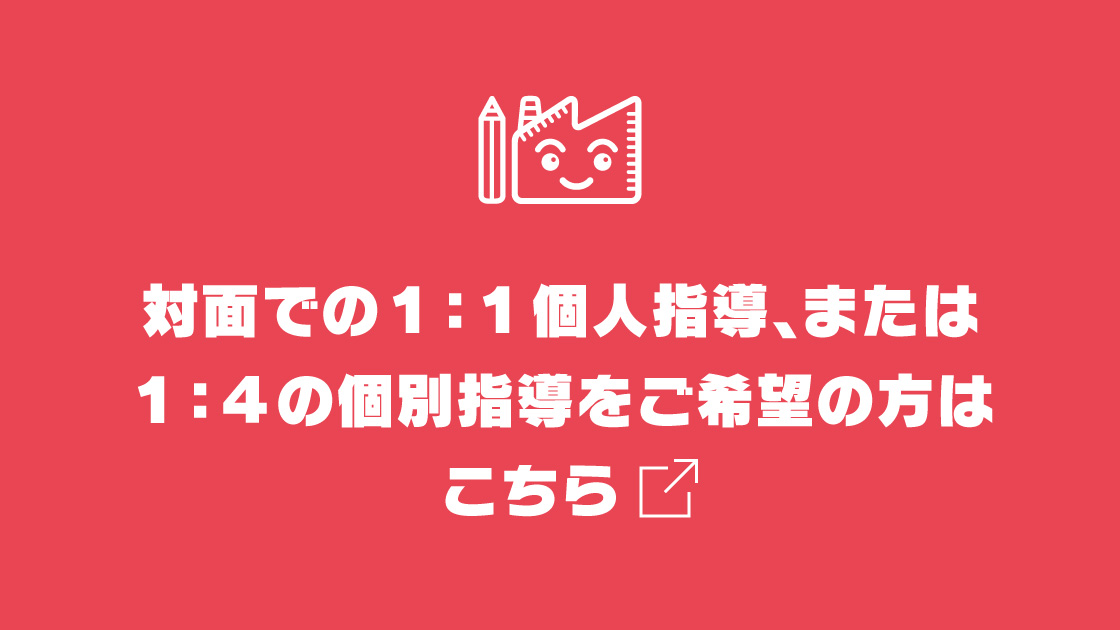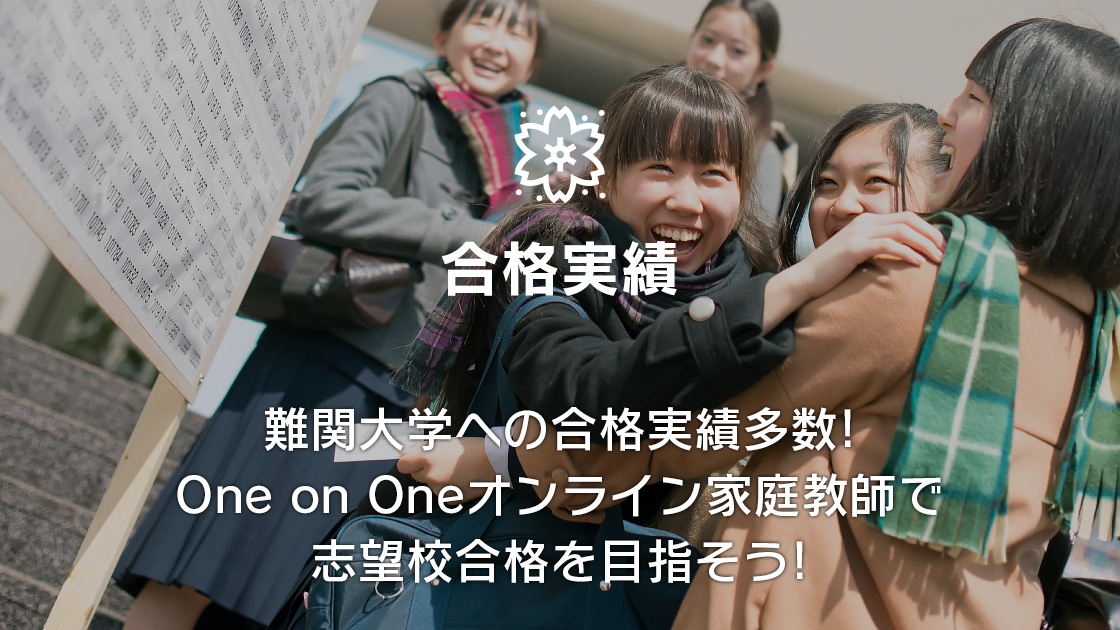友達と勝ち取った合格
オンライン家庭教師ではなく、教室での実績になります。
菅野達生くん
- 得意な科目 / 生物
- 苦手な科目 / 英語
- 将来の夢 / 研究者
- 1日の平均勉強時間 / 平日6時間 休日10時間
- 受験を1文字で表すと / 我
- 高校時代に1番夢中になったこと / 部活
- 合格を確認した瞬間の気持ち / 合格を確認した瞬間の気持ちは:ホッとした
受験舎に入るきっかけ
受験舎を知ったきっかけは何でしたか?

友達が通っていて、授業や自習室の環境がいいと聞いていました。その友達が成績がよかったのもあって、受験舎の体験授業を受けてみようかなって思いました。
実際に塾に入ってみてどうでしたか?

最初は、数学の先生以外は怖く見えていました。 しかし、講習会などで他の先生と話したり、授業を受けたりするとみんな優しくユーモアのある方ばかりで、塾に行くのが楽しく感じられるようになっていました。
実際に塾に入ってみてどうでしたか?

中学の頃に通っていた塾では定期的に先生が変わってしまい、先生とより良い関係を持つことができませんでしたが、受験舎は毎回同じ先生だったので、授業を受けるたびに良い関係を築けていました。そのため、授業中には勉強の話だけではなく、部活の話や学校の話など何でも話せる気楽さがあったので、質問もすごくしやすかったと思います。 授業では大学の情報量が多かったのもよかったです。「その大学は〇〇が出やすいよ」とか「〇〇は出にくい」など具体的なアドバイスをいただけたので、限られた時間の中でポイントを絞って対策ができました。それが合格に近づけた一番の要因だったと思います。
自習室はどれぐらい使っていましたか?

1、2年生の時はテスト前だけだったんですが、3年の夏以降はほぼ毎日使っていました。自習室はキレイで清潔感があったのがよかったです。飲食が可能だったので、長時間勉強していて小腹が減ったときには軽食をとったりできました。また、見える位置に友達がいたので、その姿を見てやる気を出したこともありました。
友達との関わり方
同じ学校の仲のいい友達が塾に多かったようですが、受験には何か影響ありましたか?

2年生の後半くらいから友達が多く塾に入ってきて初めは勉強に集中できなかったり、話したりして注意を受けたこともありましたね。
自分も何回か注意した記憶があります。

ただ、3年生になると受験への姿勢が変わり、席を離して座ったり、休憩する時には時間を決めて学習時間を減らさない、かつ休憩も入れるというのをずっと継続していました。また、学校が終わり次第一緒に自習室へ行くことが習慣になっていき、毎日欠かさずに塾に行くことができていたこともよかったんだと思います。
友達とはいい距離感で勉強できていたんですね。

はい。一人で覚えているとあまり印象に残らなかったものも、休憩中に問題を出し合ったりすることによって、知識を定着させることができましたし、友達と話していて勉強の仕方なども参考になるものもあったり、使っている参考書でおすすめのものを教えてもらったりと仲のいい友達が多くいたのでかなり助けになりました。 また、友達と話すこともとても大切だと思います。友達に相談したり、質問したりすることでストレスや不安を解消することができたし、それが勉強する意欲につながっていたと思います。
後輩へのアドバイス
高校生活を振り返ってどうでしたか?

1、2年生の頃は部活や友達と遊んでばかりいました。学校や遊びから帰ったら、疲れてしまって勉強どころではなく、テスト前に赤点を取らないようにするために勉強しているという感じでした。3年生になっていざ受験勉強を始めようとしたときに、1、2年生の内容を忘れてしまっていて、また1から始めなければいけないという始末でした。1、2年の頃からもっと日々の勉強のサイクルを作っておけばよかったと後悔しています。
受験勉強を始めて効果が出てきたと実感した時期はいつ頃でしたか?

センター試験直前ですね。やらなければならないことが多すぎて、センター試験直前に過去問を解くようになってようやく自然と手が動くようになってきたように感じました。特に数学はⅡBまでしか使わなかったので、3年生になった時にそこまでの勉強をしっかりやっておけば、さらなる高みを目指せていたのではないかと思います。
最後に、後輩へのアドバイスをお願いします。

1、2年生の時期には、今学習した範囲を忘れないように何度も復習することをおすすめします。今やっていることをしっかりと復習し、定着させていくことが、受験を乗り切るための一番の近道だと感じました。部活などで忙しい人もいると思いますが、早いうちから受験を意識し、メリハリをつけて学習時間を作ることも大事ではないかと思います。
他にも何かありますか?

模擬試験の判定を当てにしないことも重要だと思います。模擬試験の判定が悪くても、実際過去問を解いてみると意外に点数が取れるということもあったし、学校によってはポイントを絞って対策することでしっかり結果を出せることもありました。だから判定が悪くても諦めず、しっかりと対策を行っていくことが重要だと感じました。